7 結論と提言
第4章から第6章では、インドネシア、タイ、フィリピンに対するわが国の支援を4つの視点から分析した。以下ではこれらの分析に基づき、7.1で日本のアジア通貨危機支援策を評価する。7.2では、これから類似の経済危機に対する支援を実施するために考慮すべき点について述べる。
7.1.1 支援スキームの組み合わせ
支援スキームの組み合わせを分析した結果、日本のアジア通貨危機支援は、相手国の固有の経済的課題に応えるものであったと結論付けられ、柔軟性の高い政策形成を行ったと評価できる。
図7-1はその「柔軟性の高い支援」を概念的に示す図である。この図では、横軸に3ヵ国の国経済の短期的な不安定性の大小を示し、縦軸に支援全体に占める緊急無償、ノン・プロジェクト無償、プログラム借款の割合と、新宮沢構想に基づく借款におけるプログラム借款の割合の大小を示している。
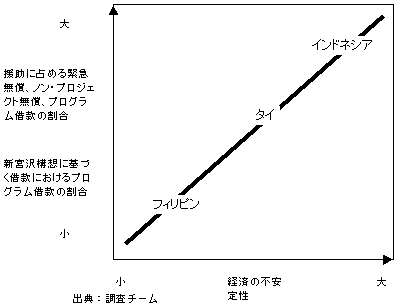
第3章で見たように、アジア通貨危機によってインドネシアとタイでは経済が安定を失い、特にインドネシア経済は民族紛争や政権交代なども相まって不安定性は大きいものとなった。一方、フィリピンでは経済は比較的安定していた。従って横軸には右側からインドネシア、タイ、フィリピンの順に並べることができる。
また縦軸には図の上から順にインドネシア、タイ、フィリピンと並べることができる。インドネシアでは、1998年、99年はプログラム援助に集中し、1998年から2000年までの円借款に占めるプログラム借款の割合(53パーセント)、1997年から2000年までの無償資金協力に占める緊急無償、ノン・プロジェクト無償食糧援助の割合(57.5パーセント)とも3ヵ国中最大となっている。一方、フィリピンに対する支援は、プロジェクト借款、プロジェクト無償が高い割合を占め、円借款に占めるプログラム借款の割合(9パーセント)、無償資金協力に占める緊急無償とノン・プロジェクト無償の割合(6パーセント)とも3ヵ国の中で最小となっている。タイに対する支援は、インドネシアとフィリピンに対する支援の中間にある(円借款に占めるプログラム借款の割合は35パーセント)。
以上をまとめると、図の右上にインドネシア、中央にタイ、左下にフィリピンとプロットできる。経済が大きく不安定化したインドネシアに対しては、緊急無償・ノン・プロジェクト無償・プログラム借款など足が速く、柔軟性が高い、雇用吸収力を持つなどの特徴をもつ支援を行い、経済の安定は失わなかったがアジア通貨危機前から経済成長軌道が低い水準であったフィリピンに対しては、プロジェクト借款を中心としたインフラ整備の支援を行った。
7.1.2 他の援助機関との役割分担
日本のアジア通貨危機に対する支援は、必要に応じて他の援助機関と支援のタイミング、支援の内容で役割分担を行い、日本独自のアジア通貨危機支援を行ったと評価できる。各国で見られた役割分担を表7-1に記す。
支援のタイミングについては、特に短期的に経済が不安定化したインドネシアとタイでは、他の援助機関の支援が一巡して手薄になった時期にプログラム借款など柔軟性の高い支援が行われた。この結果、インドネシア政府、タイ政府とも国際収支改善のための外貨や公共事業を行うための資金を確保することができた。また、緊急無償もアジア通貨危機発生後早い時期に実施しており、金額は小さいものの迅速な対応を行った。
| 支援のタイミング | 支援の内容 | |
| インドネシア | 1998年7月から1999年3月までの世界銀行・アジア開発銀行の支援が実施されていない時期に足の速く、柔軟性の高い支援を実施 | 支援スキームは類似(プログラム援助による現地労働力の活用) 支援分野は各援助機関の得意分野に特化(日本は雇用の確保や社会的弱者の救済) |
| タイ | 1998年後半から1999年前半の世界・アジア開発銀行の支援が実施されていない時期に足の速く柔軟性の高い支援を実施 | 世界銀行・アジア開発銀行は金融部門と公共部門の強化のためのプログラム援助、日本の支援は短期の経済安定化(雇用の創出)と中長期の確実な経済発展のための支援 |
| フィリピン | 1999年まではアジア通貨危機前から実施していた年次供与ベースの支援 2000年以降は、申請から実施までの期間の短縮を図った特別円借款による支援も多く実施(10件) |
支援スキームは類似(プロジェクト借款とプログラム借款を組み合わせた支援) 日本の支援はより中長期の経済発展の支援を重視 支援分野は各援助機関の得意分野に特化(日本は経済インフラの整備・治水への支援) |
出典:調査チーム
支援の内容でも、日本独自の支援を実施した。インドネシアでは各援助機関とも類似した支援スキーム(プログラム援助による現地労働力の活用)を実施したが、支援分野について世界銀行・アジア開発銀行・日本がそれぞれの得意な分野(日本の場合は雇用の確保や社会的弱者の救済)に特化した支援を行った。タイでは世界銀行・アジア開発銀行がタイの金融部門と公共部門の強化のための支援を行う一方、日本の支援は短期の経済安定化(雇用の創出)と経済発展軌道を回復するための支援を行い、特色のある支援を行った。フィリピンではインドネシアと同様に各援助機関が類似した援助スキーム(プロジェクト借款とプログラム借款を組み合わせた支援)を行いながらも、日本の支援はその得意分野(経済インフラの整備・治水への支援)に特化した支援を行った。
また、役割分担を行うだけでなく、キーとなる支援分野では他ドナーとの協力を行った。例えばタイで行われた2つの事業(社会投資事業と、経済復興・社会セクター・プログラム・ローン)では世界銀行と協調した支援を行い、経済に安定化の回復に貢献した。
7.1.3 事業の国別援助計画・国別援助方針における位置付け
日本が3国に対して実施した支援の分野は、各国の国別援助計画や国別援助方針に掲げる重点支援分野に含まれるものであり、上位計画と整合性の取れた支援が行われた。さらに、支援が多く行われた分野は、各国の経済的な課題に応えるものであったと評価できる。
表7-2は、日本が1998年度から2000年度に実施した円借款事業と、1997年度から2000年度までに実施した無償資金協力を国別援助計画・国別援助方針の重点分野ごとに分類して集計した、その上位3位である。
| インドネシア | 公平性の確保:東部インドネシア開発 公平性の確保:貧困撲滅 産業構造の再編成に対する支援:農業振興 |
| タイ | 経済基盤整備:経済インフラ整備への支援 環境保全:都市環境整備・都市交通問題への支援 社会セクター支援:社会的弱者支援 |
| フィリピン | 持続的成長のための経済体質の強化および成長制約要因の克服:経済インフラ整備 環境保全と防災:治水・砂防・地震対策への支援 格差の是正:農業・農村開発 |
インドネシアでは東部インドネシア開発14、貧困撲滅、農業振興に関する事業が多数行われた。これらは、日本の支援がインドネシアを広くカバーするものであったこと、アジア通貨危機で影響を受けた貧困層に届く支援を行ったこと、アジア通貨危機以前の不足分を輸入し、アジア通貨危機の影響により減産となった米の生産を増加させるための支援を行い、経済の安定化を目指したことを意味している。
タイでは、経済インフラ整備への支援、都市環境整備・都市交通問題への支援、社会的弱者支援に関する事業を多数実施した。これらは、日本の支援が経済発展軌道を回復するためのインフラ整備の支援を行うと同時に、短期の経済安定化のための社会的弱者への支援も行ったことを意味している。
フィリピンでは、経済インフラ整備、治水・砂防・地震対策への支援、農業・農村開発に関する事業を多数実施した。これらは、日本の支援が経済発展軌道を上昇させるためのインフラ整備の支援を行ったことを意味している。同時に災害対策や都市と農村の格差の是正など、フィリピンがアジア通貨危機前から持つ課題に対する支援も行われた。
7.1.4 相手国政府関係者の意見
タイとフィリピンで実施した政府関係者へのアンケート調査の結果、日本の支援はアジア通貨危機の克服に貢献したとの回答が両国ともに7割以上を占め、日本のアジア通貨危機支援策が高く評価されていることが明らかとなった。また、両国政府担当者が感じた支援策の具体的な便益は日本側が意図した効果と一致し、日本側が意図した政策効果が現れたと認識された。
| 表 7-3 日本のアジア支援策の具体的な便益 | ||||
|
||||
| 出典:調査チーム |
表7-3は、タイと日本で行ったアンケート調査のうち、「日本のアジア支援策の具体的な便益」に対する回答の多数を占めたものである。タイでは「雇用創出」・「タイ経済の更なる悪化からの回避」・「中長期の経済発展のための人材育成」の回答が多かった。これは、短期の経済不安定化の克服と、経済成長軌道の回復の両方を重視した日本の支援を反映したものとなっている。
また、フィリピンでは、「中長期の経済発展のためのインフラ整備」・「中長期の経済発展のための人材育成」の回答が多かった。これは、中長期の経済発展軌道の上昇を重視した日本の支援を反映したものとなっている。
7.1.5 総合評価
以上4つの視点を総合すると、日本のアジア支援策は、各国経済の課題に応えるとともに、日本独自の支援を行い、相手国政府関係者にも高い評価を得ることができたと評価できる。特にインドネシアとタイで実施された小規模プロジェクトを多数実施するプログラム借款では、雇用の創出や社会的弱者支援の面で成果をあげ、最終的に両国経済の安定化に貢献したと高く評価できる。
14 東部インドネシアとはスマトラ・ジャワ・バリを除く地域を指す言葉である。東部インドネシア開発による全国の均衡の取れた開発は、1990年代のインドネシア政府の最重要な開発目標であった。

